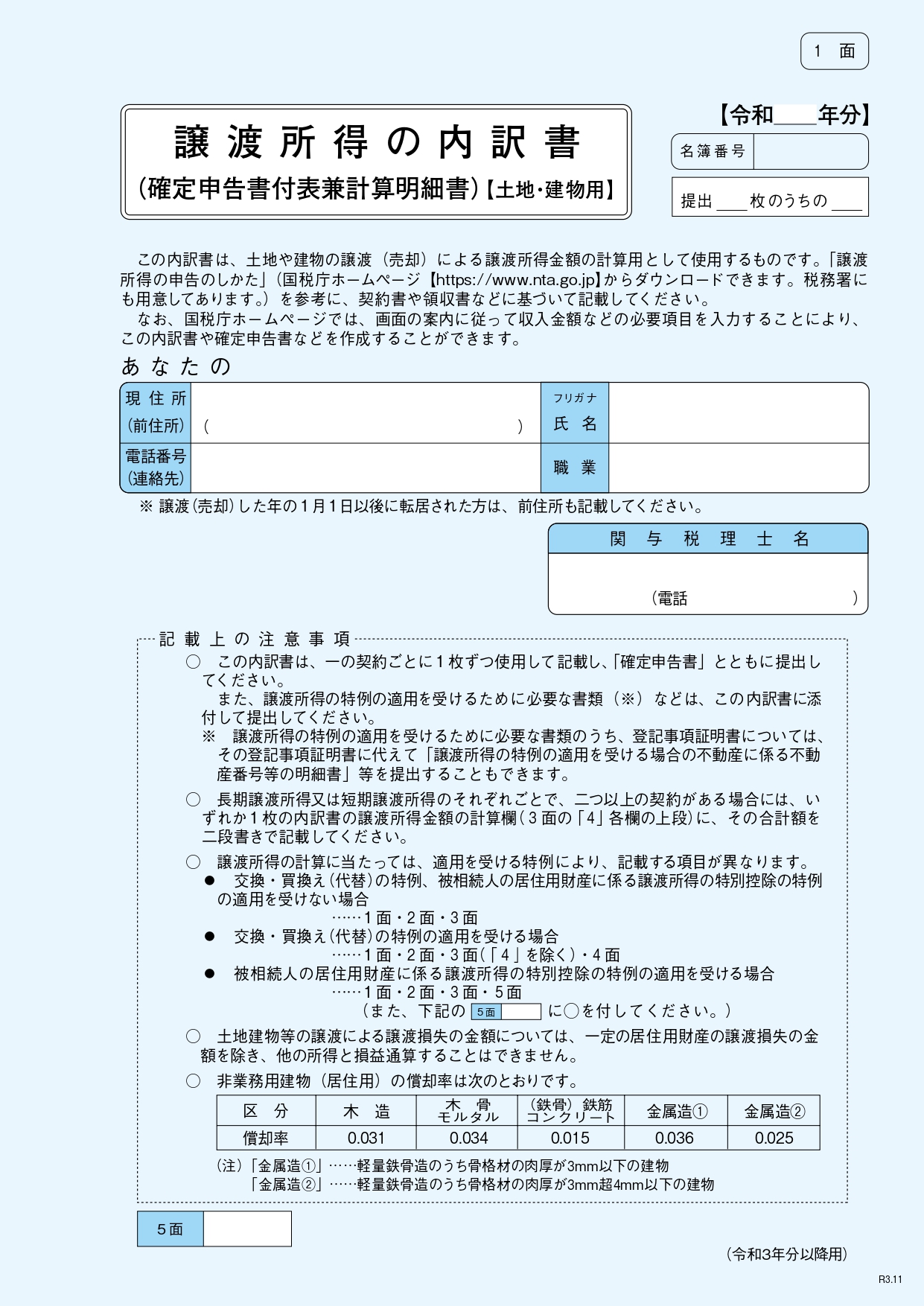債権法改正によって「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へ
2020年4月1日に民法が改正されます。
民法って?
ふだんあらためて考える事も少ないかと思いますが、実は売買、雇用、賃貸借、請負や贈与など身の周りの,日常生活の様々な場面で関わってくる各契約や,契約の解除など契約にまつわるルールなどを定めているのが民法という法律です。
契約のこと以外にも,婚姻や離婚,相続などを定めていますし,20歳未満の者を未成年(※2022年4月1日施行より18歳)と定めているのも,民法です。
私たちの日常生活のさまざまな場面で、民法という法律がルールとして働いているのです。
そんな民法ですが、民法のうち債権関係(契約等)については,明治29年(1896年)に民法が
制定された後,約120年もの間ほとんど改正がされていませんでした。
これではあまりも現代社会に合わない部分がたくさん出てきてしまっているとのことで、今回見直し
が行われることになったのです。
これにより、債権法と言われる売買契約や不法行為に関することを大幅に見直し、売買契約における
瑕疵担保責任という考え方に代わって新たに「契約不適合責任」という概念が導入されることになりま
した。これは不動産の売買契約にもとても大きな影響を与えることになります。
これまで、民法第570条などによって、瑕疵担保責任=商品に何らかの瑕疵(きず、欠陥、不適合などのトラブル)があれば売主がその責任を取らなければならないという文言通りの規定が存在しており、
①売買の目的物に普通の注意を払っても発見できないような「隠れた瑕疵」がある場合には、
②売主は損害賠償の責を負うか、瑕疵が重大で契約の目的が達せられないときは契約解除され、
③瑕疵の発生については引渡し後何年という制限もなく(実際は民法の債権消滅時効により10年で消滅し瑕疵発見後は1年以内に請求しなければならない)、
④売主の故意・過失に関わりなく責任を負うという無過失責任であったため、
売主にはとても重い責任があるとされていました。
契約不適合責任としたことにより、買主が取り得る対抗措置が、解除(契約した目的を達成できない場合)と損害賠償のみだったのが、改正民法では、追完請求=完全履行請求(第562条)と代金減額請求(第563条)も可能になりました。
今回の改正によって、契約目的の達成は可能だがハードルが高い場合には契約解除できることになり、解除できるケースが増えることが想定されます。さらに、瑕疵自体も「隠れた瑕疵」である必要がなくなったため、買主の善意・無過失は解除の要件として不要になったことも法的には比較的大きな違いとなります。
今回の民法改正は、買主保護の意味合いが強く押し出されているといって良いでしょう。
 この記事を書いた人
この記事を書いた人
PAGETOP